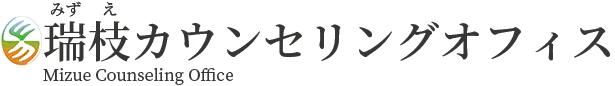Educational Content
Educational Content
教育コンテンツ
教育コンテンツ

- 2025.04.20
- No.1 内因性①(英:endogenic)
1. 定義
①:さまざまな精神の異常の中で、それを了解することのあまりの困難さのため、その背景に身体的基盤の異常が想定されるも、未だそれが確認されていない一群を意味すると同時に、その一群が共有する独特の質感をも指し示した用語。
②:さまざまな精神の異常の中で、身体メカニズムの失調が大きく関与してる一群を意味すると同時に、その失調の影響により、心的現象の階層において社会性の観点から周縁的な諸症状を生じてしまうが、その症状が共有する独特の質感をも指し示した用語。
2. 解説
内因性という用語の説明には、残念ながらとても手間がかかる。その理由は、そこに現在の精神医療の混沌が凝縮されているからだ。ならばこそ、この用語から始めよう。そして本稿は、3回分に分けた、その1回目だ。
まずは歴史的経緯からおさらいしよう。内因性とは、身体因性・心因性という用語とともに、精神疾患の分類の枠組みとして、伝統的に用いられてきた。一覧にまとめると次のようになる。1)
精神疾患の分類
身体的基盤 了解と説明 精神疾患 心因性(psycogenic) 確認されずとも臨床は可能 了解が可能 神経症 内因性(endogenic) 確認が期待されるも不明 了解を目指すも困難 統合失調症/躁うつ病 身体因性(somatogenic) 確認されている 了解は不要、説明が可能 器質性精神病など
用語の説明が必要だろう。
「了解」と「説明」とは、いずれもK・ヤスパースに由来する術語だ。これ自体が突っ込み処満載の術語だが、本稿の目的に沿った範囲で、次のように簡明に整理しておこう。
セラピストが、クライアントの言動の意味を、
・クライアントの「内から(von innen)」把握できるとき、「了解できる」と言い、
・クライアントの「外から(von außen)」把握できるとき、「説明できる」と言う。4) 5) 6)
前者は、クライアントの立場に立って、共感して・・・、という連想につながってよいのだが、これを「主観的」とまとめると、ヤスパースは怒る。精神症状の学術的研究にあたって如何に信頼性のある方法論を確立するかに腐心していたからだ。
一方、後者を「客観的」とまとめてしまうのは、まだ許される。物理学や化学を範にして、客観的に把握できる事実から、因果関係を見出す、そのイメージだ。細かな議論を抜きにした雑駁な例示なら、次のようになる。
・試験に落ちて、悲しい気持ちになっているクライアントは、了解できる。
・ウイルスに罹患して、発熱・咳嗽を認めるクライアントなら、説明できる。こんな感じだ。
でも、だからなんだ、となるだろう。ここから先は、遠回りのようだが、なぜヤスパースがこのような議論をする必要があったのか、その彼のモチベーションに迫る必要がある。そこで、身体的基盤という用語の説明を挟んだ上で、話をすすめよう。7)
身体的基盤とは、物理学的・化学的・生物学的な方法によって得られた、精神疾患の原因としての検査結果を指す。てんかん精神病の場合の脳波所見(=物理学的)、精神症状を来す甲状腺機能亢進症の場合の血液検査(=化学的)、精神症状を来す遺伝疾患の場合の遺伝子の変異(=生物学的)などが、これに該当する。
歴史的には、神経梅毒(梅毒トレポネーマという細菌の中枢神経系への感染により、記憶障害や妄想などの精神症状を来す)が身体因性の精神疾患の典型とされ、内因性の精神疾患もそれを範例に、身体的基盤の探索が精力的になされてきた。これが現在に至る生物学的精神医学の源流をなしている。「精神病は脳病である(W・グリージンガー)」が旗印だ。
しかし、20世紀の初頭、ヤスパースが『精神病理学原論』8)を出版した当時、彼にとってはその潮流が、人間のかけがえのない全体性を見失った立場として映ったようだ。その一方、ちょうどその頃、J・シャルコーのヒステリーの研究に刺激を受けたS・フロイトが、彼の精神分析学を精力的に展開し始める。当然、ヤスパースもその勢力を横目で見ながら、しかし、性的エネルギーで人間の全てを説明できるかのように断定するその論旨に、強い嫌悪感を抱いたようだ。そして足下の日々の臨床はどうか。相も変わらず、同僚たちは統一性のない、学術的にお粗末な言葉遣いで症例を語り続けている。
ヤスパースが『精神病理学原論』で自ら課したのは、生物学的精神医学でもなく、精神分析学でもない、しかし精神の異常を的確に捉えることのできる方法論の確立、これであった。もっと言うと、野放図に拡大を続ける生物学的精神医学と精神分析学それぞれに「分をわきまえろ」と制限を課したかった。だから、「了解」と「説明」という峻別を要した。
生物学的精神医学よ、お前は「説明」の範囲(身体因性)に留まれ。それを超える領域(内因性と心因性)に口出しするな。それ以上は「了解」という方法で対処するから。精神分析学よ、お前は、人間の全てが「了解可能」と安易に驕り高ぶるな。「了解不能」の領域(内因性)があることを知れ。ヤスパースの心中には常に、この二方向への痛罵が去来していただろう。彼は倫理の人なのだ。
さて、歴史のおさらいはここまでとし、精神疾患の分類の表に戻ろう。すると、初見と比べて、表が立体的に見えてはこないだろうか。ヤスパースは、身体因性にも占拠されつくさない、心因性にも占拠されつくさない、内因性という領域を確保したのだ、と。その結果の、この三分法による分類、ということになる。
この準備を経たなら、定義①が腑に落ちるだろう。と同時に、いかにやっかいな領域かも見えてこよう。身体因性のように、身体的基盤から明快にアプローチができない。かといって、心因性のように「話せばわかる」という感覚を持ちにくい。「ああ、話しても(説得しても)伝わらないな・・・」「ああ、(目の前にいるのに)遠い世界へ行ってしまった・・・」という、どうしようもない溝が、クライアントとの間に横たわっていることを肌感覚で認めざるを得ない。しかし逆に、その溝をなんとか埋めることはできないものか、その努力が、ヤスパースの「了解不能」という宣言を横目に、精神病理学という分野を支えてきたとは言える。そこには、豊かな臨床的叡智が埋蔵されているのだ。それを次世代へ、現代的な装備とともに手渡すことが、この教育コンテンツの使命の一つだ。
次回は、この内因性の領域が、現在の精神医療の現場でいかにぞんざいに扱われているかを見る。次々回で、定義②について触れよう。これが、教育コンテンツの中で提起する、内因性に対する新しい見方になる。
3. 具体例
内因性の特徴を示す、典型的な精神症状を挙げてみよう。
妄想知覚
「カトリック修道院の階段の上で、一匹の犬が直立した姿勢で私を待ち伏せしていました。私が近づくと、犬はまじめな顔で私を見て、一方の前足を高く上げました。たまたま別の通行人が数メートル先を歩いていたので、私は急いでその人に追いつき、犬は彼の前でも礼をしたのか、急いで尋ねました。その人は驚いて否定の返事をしました。それを聞いた私は、自分は明らかな啓示と関わっていると確信しました」。9)これは、K・シュナイダーによる古典的な例示だ。このシュールという他ない空気感の前で私たちは何ができるだろう。奢るなというヤスパースの忠告を胸に、しかし「了解」を試みることはできる。精神科医の安永浩が遺した「ファントム空間論」に私たちはいずれ取り組むことになるだろう。抑うつ気分
シュナイダーの例示を続けよう。「ある女性患者は『いつも胃やのどに圧迫感があります。それはしっかりとくっついていて、消えることがないかのようです。破裂しそうです、それほど胸が痛みます』と言う」。10)これは、感情としての悲しみやさみしさと質的に異なる、内因性のうつ病に特徴的な症状だ。「胸のあたりが詰まったような」とは実際、多くのクライアントが陳述する。苦悶の在りどころが精神よりも身体よりに感じられるため、シュナイダーはその質感を「生気的(vitale)」と名付けている。例はこの程度に留め、枢要な点を記しておこう。これらはいずれも「内因性」と評される精神症状で、ヤスパース的には「了解不能」なのだが、では「了解可能」の領域と、整然と区別できるものだろうか?例えば、妄想知覚の例は、了解可能な「思い込み」と、どう異なるのか?抑うつ気分の例は、了解可能な「悲しみやさみしさ」と、どう異なるのか?これこそが、精神病理学が取り組んできた課題の一つだ。あるイメージでこの問いに応えることにしよう。ここに遊泳禁止の海辺がある。波打ち際から裸足で海へ入っていく。5m進んでもまだ、海面は膝下だ。なぜ遊泳禁止なのだろう?いい海辺じゃないか?だが10m進んだところで急に足の裏から砂の感覚が消失すると、あごまで海面が迫りやっと海底が足に着いた。この感覚だ。地続きなのだが、落差がある。これが内因性の領域の鳥羽口だ。この落差への感度を上げることが、精神科ユーザーをサポートしていく上で必須のスキルとなる。
4. 関連用語
定義②に用いた見慣れない用語に最低限、説明を加えておくべきだろう。
暗黙知理論(theory of tacit knowing)
物理化学者のM・ポランニーが提唱し、経済人類学者の栗本慎一郎が継承・拡充した、ヒトが何かを知るとはいかなる事態かについての根源的な分析を踏まえ、暗黙知(tacit knowing)という概念を用いて、多岐に渡る現象を一貫した視座で捉えることに成功している、哲学的思想を言う。具体的には、日常的な相貌の認知や道具の使用から、科学的発見に至るまで、そこに共通の構造を取り出して議論を展開している。暗黙知(tacit knowing)
暗黙的(tacit)という用語でポランニーは、その振る舞いを明示的(explicit)に分節化はできないが、その存在を想定せざるを得ない、私たち人間すべてに備わっている、あるメカニズムについて語ろうとしている。それは決して「オカルト」や「超能力」と紐付けるべき概念ではない。誰しもが無自覚だが日常的に活用しているからだ。それは典型的には、私たちが何かを「知ろうする(knowing)」営みの中であらわになる。例えば、街ですれ違った見覚えのある顔が、誰であるかを「知ろうとする」場面を思い出してみよう。瞬時に私たちは「あ、○○さんだ」とひらめく。しかし何を根拠に、その人の顔のどのパーツのどの特徴をもってそう判断したのか、明示的に言語化することは難しい。改めて問われるなら「なんとなく、あのちょっとタレ目の感じと・・・いや、なんというか、あの口元の感じとか・・・」などと口ごもる他ない。しかし「私たちは語れる以上のことを知っている」11) ゆえに「○○さんだ」と「知る」ことができる。その根拠の言語化が困難であるにもかかわらず、その判断の確かさは揺るぐことがない。このような認知を可能にするメカニズムに対して、ポランニーは「暗黙知」という名称を与えた。層の理論(theory of levels)
暗黙知理論に含まれる、世界を階層構造として捉える認識の枠組みを指す。類例は他の思想家にもあり、下位の層から上位の層が創発(emergence)すると理解する点では共通だが、その創発の機序を、暗黙知から一貫して描きだしている点が出色である。教育コンテンツでは、便宜的にその階層構造を、下位から上位への順に、次のように設定しておく。物理学的な層→化学的な層→生物学的な層→身体→身体メカニズム→心的現象→社会的現象。身体メカニズム(body mechanism)
層の理論の中で、身体より上位、心的現象より下位の層を指す。いわば「からだ以上、こころ未満」の層を指し示していることになる。この層の存在を設定することの妥当性については、多くの臨床的な知見を援用することができる。一つは、幻肢という臨床症状だ。そして、それをヒントにした、統合失調症の病態仮説としてのファントム空間論(安永浩)も、身体メカニズムの層を結果的に予告している。哲学者のM・メルロ=ポンティを踏まえて展開中の認知神経リハビリテーションという、脳梗塞などを対象としたリハビリテーションの臨床も大いに参照に値する。教育コンテンツの中では、内因性とは、この身体メカニズムの失調が大きく関与しているものと捉える。コネクトーム(connectome)
神経系を構成する神経細胞が相互に接続することによりできあがる神経回路を言う。ここで関連するのは、物理的な接続の次元ではなく、その上位の、神経細胞群の機能的な神経回路(functional connectome)である。精神疾患との関連性が指摘されるDMN(default mode network)などはその一例。教育コンテンツの中では、身体メカニズムを具体的に担っている存在としてコネクト−ムを取り上げる。
5. 展開
心因性に分類される疾患や病態の中にも「了解不能」と感じられる局面は多い。例えば、心因性(神経症)に分類される強迫性障害は、重度の場合、とても「話せばわかる」という病状ではなくなる。その状態では、身体メカニズムが失調を来していると考えられる。いわば、心因性が内因性にスライドしていく、ということだ。
つまり、内因性が指し示す領域を、次のように捉えると見通しがよいだろう。身体メカニズムに失調を来した結果、一つ上位の心的現象の層に異変が生じ、その層において了解可能だった言動が、了解不能の周縁領域に逸脱していく、その垂直方向と水平方向のダイナミズムが交錯する領域であると。
6. 活用法
臨床
・心理教育の一つの柱として、内因性の病状に関する情報提供は重要だろう。クライアントは、自身に起きている変化を当然ながら、未知のものとして、大なり小なり恐れおののいている。その緩和は、療養をすすめていく上での土台となる。ただし、これから教育コンテンツで展開される内容をそのまま伝えるわけにはいかない。わかりやすい例示が必要だ。・例えば、抑うつ状態なら、自転車のチェーンが外れた状態と例える心理教育を用意している。→ 「うつ病の治し方で最初に知るべき3項目 その1」(クライアント用教育コンテンツ)・また、躁うつ病の教育コンテンツでは、二つの状態像(抑うつ状態と躁状態)について、ヒトの4つの機能というフレーム(認知の枠組み)から整理している。→ 「もやもや解消!躁うつ病シリーズ その1 人の4つの機能とは」「もやもや解消!躁うつ病シリーズ その2 感情と気分を区別しよう」(いずれもクライアント用教育コンテンツ)・躁うつ病を、地下室・地上の一階・その上の二階からなる家屋に例える場合も多い。一階に居ながら強い感情を抱えきれず中庸気分を維持できない場合、一階の床が抜けて地下室(抑うつ状態)に陥るか、二階(躁状態)に移ってしまうか、と説明する。階を移動するというイメージで、内因性の領域にスリップしていく様を共有するわけだ。カンファレンス
・内因性という用語が現在の精神医療で被っている実情を活写している一文を引用しよう。(「外因」を「身体因性」として、また「デバイス」を「知的用具」と、読み替えてよい。)
「心因/内因/外因 精神医学におけるレトロ・デバイスの代表。ベテラン医師がカンファレンスでこういう用語を発言すると、中堅医師は苦虫をかみつぶしたような顔をし、若手医師はきょとんとする、という概念デバイス。グローバル化(つまり米国中心)の時代には、ガラパゴス的デバイスとして低い評価を受けている。上記のようなカンファの場面になんども遭遇した上級医は、決して公の場では「内因」などとは口走らないようにして、しかし、自分の臨床では重宝してこっそりと使っている」。12)
・しかし、ここまでの議論を経た私たちなら、堂々と口にしてよいだろう。例えば、次のような(架空の)カンファレンスでの発言はどうだろう。
A:「典型的な緊張病状態で発症したのですが、寛解して、障害者雇用で就労されましたが、上司からのキツい叱責をきっかけに、離人感を訴えるようになった、統合失調症の方です。その後、次のような症状があって困っていると。『街で人とすれ違う時、その人に見られているというより、自分が自分を見ている感じがする』と。これは、解離の一環なのか、内因性の病状なのでしょうか?」
B:「症例提示、ありがとうございます。つまり、高校の時は反応性に短期間、抑うつ状態になったが、立ち直って無事、大学に合格した。でも、また秋学期から似たような状態になっている。登校して、学業には集中できているが、本人の面接での様子がなんともスッキリしない。今回は内因性の病状に移行しているのではないか、ということですね?」
7. Do/Don't
Do
・内因性という用語が指し示すものが、精神医療の中核の標的だと考える。・そこには大きく、二つのテーマが交錯している。一つは、身体メカニズム(とその失調)が、精神医療の主題(subject matter)だということ。(身体の層における失調は、それぞれの身体科の主題であり、心的現象の層における失調は、臨床心理学の主題である。)もう一つは、その失調の結果、一つ上位の層である心的現象に、安易な了解を拒む精神症状が生じるが、それも同じく、精神医療の主題だ、ということ。Don't
・内因性という用語を死語、ないしはジャーゴンと見なす。
8. 註・参考文献
1):この表は、2)、3)をもとに若干の改変を加えた。ヤスパースはこのような表を用いてはいないが、彼の主張はこのように整理はできる。
2):内海健, 兼本浩祐編:精神科シンプトマトロジー. p154, 医学書院, 東京, 2021.
3):古茶大樹:臨床精神病理学. p63,日本評論社(Kindle版), 東京, 2019.
4):Jaspers,K. : General Psychopathology VolⅠ(trans: Hoenig, J, Hamliton, M.W.). p28, The Johns Hopkins University Press, Baltimore,1997.
5):Jaspers,K. : Allgemeine Psychopathologie. p24, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1948.
6):ヤスパース:精神病理学総論 上巻. 内村祐之, 西丸四方他訳. p41, 岩波書店, 東京, 1953.
7):身体的基盤とは3)で用意されている用語ではあるが、歴史的な術語ではない。
8):5)の初版
9):クルト・シュナイダー:新版 臨床精神病理学. p92, 文光堂, 東京,2007.
10):クルト・シュナイダー:新版 臨床精神病理学. p127, 文光堂, 東京,2007.
11) :Polanyi, M:The Tacit Dimension. p4, The University of Chicago Press, Chicago, 1966.
12):村井俊哉:精神医学の概念デバイス. p74, 創元社, 大阪, 2018.
9. 改訂
R7/4/14 公開
RECOMMEND